液体の沸騰と沸点は、危険物取扱者試験において重要な物理化学の知識の一つです。特に、第4類危険物(可燃性液体)の扱いでは、沸点の違いによる危険性の違いを理解することが求められます。本記事では、沸騰のメカニズムと沸点の性質について詳しく解説し、試験対策として役立つ知識を提供します。
沸騰と沸点の基本概念
飽和蒸気圧: 液体が蒸発して気体になるとき、気体分子が液体表面から飛び出します。一定温度で液体と気体が平衡状態に達したときの気体の圧力を「飽和蒸気圧」といいます。液体の温度が上昇すると、この飽和蒸気圧も増大します。
沸点: 液体の飽和蒸気圧が外部圧力(通常は大気圧)と等しくなったときの温度を「沸点」といいます。つまり、外圧が低いと沸点も低くなり、外圧が高いと沸点は高くなります。
沸点と危険物の関係
危険物の分類の中でも、第4類危険物(引火性液体)の多くは、比較的低い沸点を持ちます。これは、低い温度でも蒸発しやすく、可燃性の蒸気を発生しやすいことを意味します。例えば、ガソリンの沸点は約30~220℃と幅がありますが、常温で十分に蒸発するため、引火の危険が高いです。一方、灯油の沸点は150~250℃と高く、ガソリンよりも蒸発しにくい性質を持っています。
日常例で理解する沸騰と沸点
沸点が外圧によって変化することは、日常生活の中でも観察できます。例えば、標高の高い山では気圧が低いため、水の沸点が100℃よりも低くなります。そのため、高山で料理をすると、水の温度が上がりにくく、調理時間が長くなります。また、圧力鍋では内部の圧力を高めることで水の沸点を100℃以上にし、調理時間を短縮します。
試験に関連するポイント
危険物取扱者試験では、沸点に関する問題がよく出題されます。以下のポイントを押さえておきましょう。
試験対策のポイント
- 飽和蒸気圧と温度: 温度が上がると飽和蒸気圧は増大し、外圧と等しくなると沸騰が始まる。
- 外圧と沸点の関係: 外圧が低いと沸点は低くなり、高いと沸点は高くなる。
- 引火性液体の危険性: 沸点が低い液体ほど蒸発しやすく、可燃性蒸気を発生しやすいため、火気厳禁の環境で取り扱う必要がある。
- 実生活での応用: 圧力鍋や高地での調理の例から、外圧と沸点の関係を理解する。
試験問題例
沸点についての説明のうち、誤っているものはどれか?
(1) 水に不揮発性物質が溶けると、沸点が上昇する。
(2) 沸点の低い物質ほど蒸発しにくい。
(3) 純粋の沸点は、1気圧のとき100℃である。
(4) 液体の蒸気圧が大気圧と等しくなった時、沸騰する 。
(5) 液体の沸点は気圧によって変わる。
答え: (2)沸点が低いほど、蒸発しやすい。
解説
液体の蒸発しやすさは、飽和蒸気圧に影響されます。一般に、沸点が高い液体は飽和蒸気圧が低く、常温では蒸発しにくい性質があります。例えば、ガソリンは沸点が低いため常温で蒸発しやすいですが、灯油は沸点が高いため蒸発しにくいです。
液体の沸点は、外圧が低いと液体の沸点は高くなる。これは正しいか誤りか?
答え: 誤り
解説
液体の沸点は、外圧が低くなると低くなり、外圧が高くなると高くなります。例えば、標高の高い場所では気圧が低いため、水の沸点は100℃よりも低くなります。このため、「外圧が低いと液体の沸点は高くなる」という記述は誤りです。
まとめ
液体の沸点は外圧によって変化し、沸点の低い物質ほど蒸発しやすくなります。特に第4類危険物は低い沸点を持つものが多く、適切な保管と取り扱いが求められます。試験では、沸点と外圧の関係や、引火性液体の危険性についての理解が重要です。日常生活の例を活用しながら、しっかりと知識を身につけましょう。
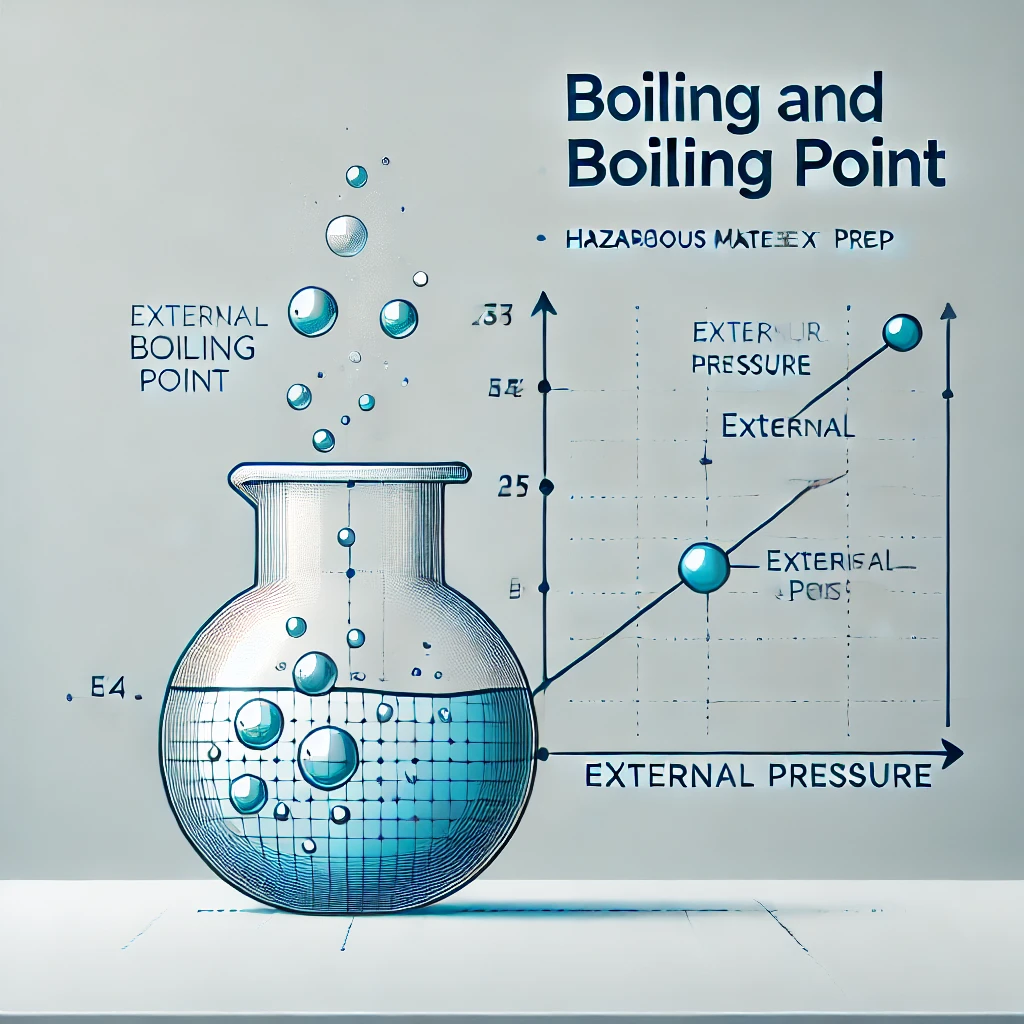


コメント